きみの成年後見支援センター
こんな心配はありませんか?

成年後見制度の
マスコット
後見ちゃん
・お金や通帳、印鑑等の管理ができない。なくしてしまう。
・ひとりでは書類の手続きができない。
・相続手続きをしたいけど、認知症があってできない。
・金銭搾取を受けているかもしれない。
・よくわからないまま、訪問販売にお金を支払ってしまう。
・子に障害があり、親なき後が心配。
ご相談ください
きみの成年後見支援センターでは、認知症や知的障害、精神障害などの理由により、物事を判断することに難しさや不安のある人の権利を守り、安心して自分らしく暮らせるよう、支援します。
生活する上での困りごとを一緒に考え、成年後見制度をはじめ、その他必要な制度やサービスにつながるよう、手続きのサポートや関係機関との調整を行います。
また、成年後見制度の利用に必要な手続き費用、後見人等への報酬の助成も行っています。
お気軽にご相談ください。
きみの成年後見支援センター(保健福祉課内)
電話:073-489-9960(平日 8時30分から17時15分)
きみの成年後見支援センターのご案内(パンフレット)(PDFファイル:12.3MB)

成年後見制度とは
知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることが心配な人の思いを地域みんなで分かち合い、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
家庭裁判所が選任した後見人等が本人の預貯金などを管理したり、本人の希望や体の状態、生活の様子などを考慮して、必要な福祉サービスなどが受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いなどを支援します。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
|
|
法定後見制度 |
任意後見制度 |
|
制度概要 |
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度(本人の判断能力に応じて、「後見」「補佐」「補助」の3つの制度があります) |
将来、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ自分が決めた代理人(任意後見人)と契約し、その代理人にお願いしたい事務(本人の生活、療養看護や財産管理など)の内容を決めておき、判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度 |
|
申立手続 |
家庭裁判所に申立てを行う |
1.本人と任意後見人となる方との間で、依頼する事務について、任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を、公証人が作成する公正証書により締結 2.本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申立てを行う |
|
申立てができる方 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など |
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方 |
詳しくは、下記バナーから厚生労働省「成年後見早わかりサイト」へ
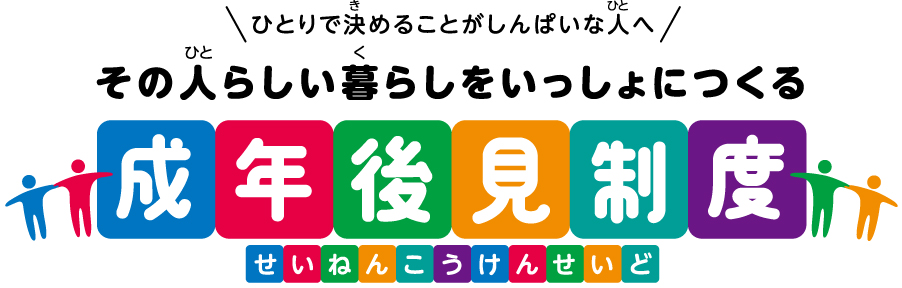
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ






更新日:2025年08月06日